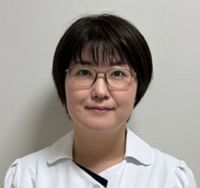大学院生からのメッセージ
専門職としてのスキルアップと勇気をくれた、MPHプログラムでの2年間
|
|
中﨑 真也 さん 健康科学研究科 博士前期課程 保健・医療・福祉政策システム領域 公衆衛生研究室(2025年 3月修了) 2024年度 最優秀学修賞 受賞 |
私は公衆衛生学修士(Master of Public Health, MPH)プログラムの第1期生として本学で学びました。本学大学院には医療・保健・福祉・行政など多様な専門職が集い、現場の問いを研究で解く力を養います。
私自身、青森県のへき地医療に従事する中で、研究経験の乏しさを課題に感じていました。その臨床経験を終え、キャリアを見つめ直していた時期に、MPHプログラムの新設を知りました。当時、他県に住んでいたため、生活基盤を変えずに学べるオンライン型のスタイルに惹かれ、入学を決意しました。遠隔教育に精通した教職員の方々のおかげで、地理的な制約なく学業に集中できました。授業欠席時にもオンデマンド視聴で補完できる点も支えとなりました。
授業は発表・討論が中心で、本学教員のみならず、全国から招かれた著名な外部講師も担当されています。この質の高い講義のもとで、多職種の院生が互いの経験を持ち寄り弱点を補い合いながら、知を深めていきました。加えて、論文の批判的読解、統計ソフトを用いた分析手法、アカデミックライティングといったスキルも体系的に学びました。疫学・統計学から健康危機管理、保健政策、行動科学など幅広い分野を横断的に学んだことで、それまでばらばらだった知識が有機的に結びつき、分野を超えた思考の広がりを実感できました。
そして、この2年間の学びの集大成が、特別研究と修士論文の執筆でした。指導教員の丁寧な伴走のもと、医療安全をテーマにオンラインアンケート調査に挑戦しました。本学には全員に支給される院生研究費、選考による追加助成金、論文投稿費用の助成など手厚い研究支援制度があり、私の挑戦も支えてくれました。自分の考えを形にする経験を通して、研究を実践する能力の土台を築けたと感じています。
本学大学院は講義の充実度が高く、他分野の修士や博士の学位を既にお持ちの方にとっても、きっと新たな発見があるでしょう。皆さんも、地球上どこからでも学べる本学大学院で、新たな一歩を踏み出してみませんか。私は今も、研究成果の論文化に取り組み、次のステージへの挑戦を続けています。その勇気を与えてくれたのが、本学大学院での2年間です。
専門看護師としての思考過程を育み、看護の力を探求した2年間の学び
|
|
越後 優子 さん 健康科学研究科 博士前期課程 (2020年 3月 修了) がん相談支援センター |
私は病棟勤務をする中でがん治療を受ける患者・家族へのケアが十分にできていないと感じることが増え悩んでいました。その時、青森県立保健大学大学院にがん看護CNSコースができることを知り、進学を決意しました。在学中は知識を得るとともに、自身の経験を振り返ることを基盤に、大学院生や講師の先生方とディスカッションを重ね、学びを深めました。患者の強みを捉え、複雑な問題を解決するために専門看護師としての役割を発揮して介入するかを常に考えました。子育てをしながらの進学でしたが、時間の使い方を工夫しながら充実した学業を中心とした生活を送ることができました。
県外での病院実習は、他施設で看護実践をした貴重な経験でした。講義を経て、自身の成長を実感していても、実習指導者の専門看護師の考えの幅の広さに圧倒されましたが、学び続けることの意味も教えていただきました。
大学院修了後は、病院に戻りがん看護専門看護師として外来看護に重点を置いて活動しています。患者が納得した治療を安心して受けられるように、外来診察に同席し、看護師と協働して意思決定支援やがん薬物療法を受けるうえでのセルフケア支援をしています。また患者が安心して最後まで自分らしく生活できるように地域の医療機関との連携を調整し在宅移行支援も積極的に行っています。さらに、ともに働く看護師が楽しくやりがいをもって看護ができるように心がけて関わりをもつようにしています。臨床現場での課題に対しては、大学院で学んだ思考過程や研究的思考を思い出し、俯瞰的視点をもって専門看護師としての役割を考え、課題が解決できるように実践し経験を積み重ねています。
がん患者はこれからも増加し、がん治療も遺伝子検査に基づいた治療の選択から療養場所の選択など、さまざまな場面で意思決定支援が必要となり、病院だけではなく地域としてよりよい医療やケアを提供することを追求していきたいと考えています。
|
|
菅原 陸 さん 健康科学研究科 博士前期課程 対人ケア領域 スポーツリハビリテーション学研究室 (2023年 3月 修了) 青森県スポーツ科学センター |
私は、青森県立保健大学の理学療法学科から引き続き大学院へ進学しました。
学部生のころから陸上競技のスポーツリハビリテーションに興味がありました。またデータを集めたり、数字をみたりすることが好きだったため、研究分野にも興味を抱いていました。一度臨床に出て経験を積んでから、大学院に進学することも考えましたが、私自身後回しにしやすい性格であり、ストレートで進学しなければもう機会はないし、後悔することが目に見えていたため、大学院への進学を決意しました。
進学を選んだことは正解だったと感じています。私の所属していた研究室ではアーチェリーやバスケットボール、パラスキーなど様々なスポーツに関わる機会やスポーツ関連の学会への参加機会が多くあり、自分の視野や技術、知識を養うことができました。加えて、様々な人との関わり方や日程の調整の仕方など社会で活動していく上で必要なことも学ぶことができました。また大学院内では、他の研究室の院生や先生方との文献検討や研究に関してのディスカッションを行う時間が多くあり、自分一人では気づくことができなかった客観的な視点、考え方を養うことができました。
大学院修了後は、青森県スポーツ科学センターの動作分析専門員として働き、県内の高校生の競技力向上を支援しています。各競技に適したサポートを考える必要があり大変なことも多いですが、大学院時代の経験が今の私の活動を支えていると感じています。また、実際に青森のスポーツ選手や団体に関わったことで、今まで見えていなかった臨床現場での課題が浮かび上がってきました。その課題に対し、寄り添い、解決し、対策方法を広めるためには、後期博士課程への進学が必要だと考えるようになりました。
前期博士課程での2年間は慣れないことや辛いことも多くありましたが、確実に私がやりたいことを実現させるために必要な時間であったと言えます。進学をすることに対して不安や恐怖心を抱く方もいるかと思いますが、私は自分を信じて進んでみることをお勧めします。
試す価値は?
|
|
吉水 春菜 さん 健康科学研究科 博士前期課程 (2025年 3月 修了) 食と水の検査センター |
私は、本学栄養学科を卒業後に就職し、社会人2年目のタイミングで社会人院生として大学院に進学しました。大変すぎて後悔する日が来るだろうという想像は容易にできましたが、それでも大学院に進学した理由は、単純な知的好奇心と考える力、判断する力を養いたいと思ったからです。もともとは大学院に行くなんて考えもしませんでしたが、学部時代の卒業研究において答えのない問いに対して考え、道筋を立てて科学的に答えを求めていくことの面白さは感じることがありました。しかし、大学卒業後は就職することを当初から考えていたため、一度就職してそれでも院に進学してみたいと思うのなら進学を考えようと決めて社会人生活をスタートしました。
働く中で思ったことは、自分で考える力と正しく判断する力の必要性です。なぜ?どうすればいい?という疑問や問いに対して、情報を収集・整理し、考え、実行・判断する、この繰り返しが答えを求める中で必要なことであると感じました。また、こうやったらどうなる?というようなアイデアを持つには、考える源となるさまざまな知識や視点、ちょっとの好奇心が必要ではないかと考えました。このようなことを思いながら過ごしていると、やっぱり院に進学してみようかなと思い、実際に行動してみることにしました。
働きながらの大学院生活は充実しすぎなくらい充実していました。講義では、さまざまなバックグラウンドを持つ院生の皆さんと共に学ぶことで、新たな視点や考えを知り、とても良い刺激をもらいました。また自身の研究では、まだ答えのない問いに対して仮説を立て、実験、分析、考察し、結論を導くという研究の基礎を学ぶことができました。時間に追われることも多々ありましたが、大学院の先生方、同じゼミの学部生たち、職場の方々のサポートの下、考える力、判断する力を鍛えながら、進学しなければ得られなかった多くの経験を積むができました。
大学院に進学しなくても学べることは多く、進学して学ぶことが全てではありませんが、少しでも興味があるなら行ってみる価値はあるのだと思います。何を選択するのかは自分次第ですが、大学院進学を学びの選択肢に入れてみても良いのかもしれません。